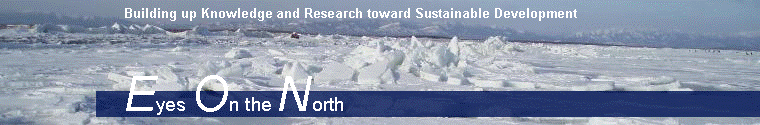日
本海は,日本列島に沿って暖流である対馬海流が北上し,冬でも比較的水温が高い.この対馬海流は,沖縄周辺で黒潮が東シナ海側に分岐して北上,対馬海峡を
へて日本海に入り,日本列島沿岸に沿って北上する暖流である.その大部分は津軽海峡を通って太平洋に流出するが,一部はさらに北海道沿岸を北上して宗谷海
峡を通り,オホーツク海に流出する.このおかげで,北海道の沿岸では,日本海側の海水温が高くなる.
しかし宗谷海峡あたりまで北上すると,今度は北から寒流であるリマン海流が,間宮海峡・タタール海峡から南下してくる.リマン海流は,日本海を北上す
る対馬海流が北部日本海で大陸からの寒気によって冷やされ,これにアムール川河口から間宮海峡をへて日本海へ流れ込む淡水と混合して南下し,沿海州沿岸に
沿って北緯40度付近まで到達する寒流であると考えられている.図は,気象庁による北西太平洋における1971~2000年までの30年間の2月の平均的
な海面水温の分布である.タタール海峡を南下し,サハリン島南端から沿海州沿岸にかけての日本海に,低水温の領域が広がっているのが確認できる.また同図
からは,その南側を対馬暖流が北海道沿岸に北上する様子も想像できる.こうして見ると,日本の日本海沿岸地域にとっては,対馬暖流は,厳冬期には大陸から
の寒気を受け止めて緩和してくれる緩衝作用を担っていることがよくわかる.


図1: 2月の平均海面水温(1971-2000):気象庁,http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/kaikyo/knowledge/sst.html
オ ホーツク海だけでなく,上記のリマン海流が卓越するタタール海峡付近の日本海北端部も,厳冬期には海氷が出現する.間宮海峡の中央より少し北にアムール川 の河口があり,大量の淡水が流出してくる.アムール川河口域となる間宮海峡部は,南北の長さ約160km,幅は最大で40km,オホーツク海側の出口で 18.5km,日本海側の最も狭いところの幅は7.5km,水深は3-4.5m程度,場所によっては2mに満たないほどの非常に浅い閉鎖性水域を形成して いる.アムール川の河川水のために塩分濃度が非常に低く,フナやコイなどの淡水魚も生息するという.浅くて冷えやすく,塩分濃度が低いために結氷温度が高 いことに加え,大陸からの寒気の影響を受けて,この水域はオホーツク海の中で最も初期に結氷する水域とほぼ同時に氷り始める.平均して11月から氷り始 め,その後約半年間にわたって海氷に閉ざされる(JANSROP-GISなど).そして5月から6月にかけて,やっと海氷が消滅するという.
こ の水域の南に続くタタール海峡も同様に,冬には北から徐々に結氷域が南に広がっていく.タタール海峡の北部では,サハリン島西海岸の北から1/4あたり (北緯49度位)までは,サハリン島から大陸までの広い範囲で海氷が出現する.さらに,サハリン島西岸の南端から北海道北端部の稚内近傍までの海上で,海 氷が出現する.大陸沿岸となる西側は,ロシアハバロフスク州および沿海州沿岸に沿ってさらに南下し,北緯43度付近まで海氷が見られる場合がある.
ま たサハリン島西岸では,北から3/4位(北緯48度あたり)までは沿岸に定着氷が生成される.このサハリン島西岸は日本海に直接面した比較的単調な海岸の ため,波浪などの外力によって破壊された海氷が積み重なって厚くなった氷丘や氷丘脈ができることもある.定着氷の厚さは,北部では0.7m~1.0m程度にまで発 達するところもある.定着氷の沖では,その場で結氷してできた氷盤や,北から海流や風によって流下してきた氷群が漂流する.海氷が存在する期間は,北緯51度付近で最小4カ月・最大6カ月,北緯49度付近で最小2カ月・最大5.5カ月にわたる.
シャフチョルスク近郊(サハリン西岸)の定着氷
ウグレゴルスク近郊(サハリン西岸)の海岸
ウグレゴルスク近郊(サハリン西岸)海岸の定着氷(上写真と同じ場所の冬の様子)
イリンスキー近郊(サハリン西岸)海岸の定着氷と漂流する氷群