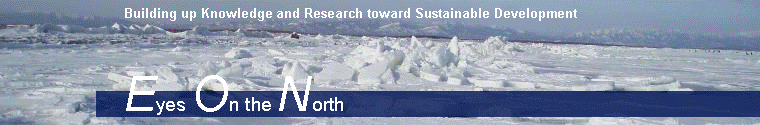
|
■極東ロシアの地勢 ■地 勢 極東ロシアの南北中央に
はスタノボイ山脈がバイカル湖近傍からオホーツク海に向かって東西に走り,地域を2分している.ス
タノボイ山脈から南の部分は,ハバロフスク地方,アムール州,沿海地方となる.一方スタノボイ山脈の北には,レナ川が東へ,のちに北に向かって流れる
広大なヤクート低地が北極海に向かって広がっている.この平野の東端には,オホーツク海にぶつかったスタノボイ山脈が北に偏向して連なるベルホヤンスキー
山脈,その東にはチェルスキー山地およびコリマ高地が続く.このように極東ロシア北部は,全体的にオホーツク海に面した南部に険しく,内陸部より北極海に
向かって平野部が広がっている.地面には凍土が広く分布する. 気候は寒冷で,内陸高地のオイミヤコンという村は,北半球における最低気温の世界記録を記録した(-72度).ヤクーツクなどの内陸部低地でも,冬は-60度に達することがある.一方夏は,7月の短い期間ではあるが30度を超える日があり,気温の年較差が100度に達するほどになる. ■交通網北極海側の主な都市は,サハ共和国の首都ヤ クーツク,レナ河の河川輸送拠点レンスク,ダイヤモンド産地のミールヌイ,南部の石炭生産と交通の要地タモットなど.また,北極海に面した海岸にはティク シ,ペベクなどの小さな港町がある.これらの港町はいずれも孤立しており,主たる交通は飛行機か船である.また内陸地に散在する町や集落の多くは大河に沿っ て立地しており,その主要交通手段はレナ川およびその支流などを利用した河川の舟運である.長距離の道路網は,サハ共和国のヤクーツクを中心に,西のミー ルヌイに向かう道路がある.東方向はアルダン川からコリマ高地を越えてマガダンまでの道路(コリマ街道)がある(これはまだ全線は開通していない).南に向かう道路が もっとも確実で,ヤクーツクからBAM鉄道に接続する支線のあるティンダまでつながっている.また,数年前まで極東ロシアから西シベリア,ひいてはモスク ワまでつながる道路はなく(車がなんとか走れるという意味で),旅人の間では”Zilov Gap”と呼ばれていた.近年,これをつなぐ幹線道路”Amur(ハバロフスク~チタ)”の建設工事が進められ,都市間・地域間のギャップが埋められよう とされている. 一方,ス タノボイ山脈から南のハバロフスク地方,アムール州,沿海地方はロシア極東地域の中では,人口が集まっているとともに産業化が進んだ地域となっている.沿 海州は日本海への玄関として,ウラジオストク,ナホトカ,ポシェットなどの港湾を擁し,シベリア鉄道および連邦道路にて内陸のハバロフスクやコムソモルス ク・ナ・アムールなどの都市とつながっている. ハバロフスク州は,日本海・太平洋への玄関である沿海州と,シベリアやウラル地方およびその西のヨーロッパ方面へと続くシベリア鉄道の要衝となっている.同時に,BAM鉄道の日本海側の終点であるワニノおよびソフガワニの港湾都市を擁し,東シベリア地域の天然資源の輸送路として期待されている. オホーツク海の北縁に位置するマガダン州は,冬期にはオホーツク海沿岸が流氷に閉ざされ,背後には険しいコリマ高地を控え,交通網からは隔絶された状態にある.コリマ高地を抜けてサハ共和国へと続くコリマ街道は,険しく危険な道路として知られる. このように道路網や鉄道網が未発達であるのは,地盤が凍土に覆われていること,遠く離れた拠点間には険しい山地,広大な湿地,膨大な数の河川が存在することなどの理由による.さら にこれに追い打ちをかけたのが,以前の経済停滞と予算不足であった.凍土は夏になると融解して手がつけられなくなる.また長い時間にわたって荷重を受けると地盤 の沈下・変形が発生する.従って交通網を建設するのも大変であるが,さらに毎年多大な補修を行う必要があるのである.ただし,これらの障害を逆手にとっ て,冬期には凍結した原野・湿地や河川を通る“冬の道路”も利用されている.橋がほとんどないため,夏には船でなければ不可能なレナ河などの河川横断が, 冬には容易になる. 一方近年では,石油価格や天然資源高騰を背景としたロシアの経済発展により,輸送関連インフラへの予算・投資が活発になり,次々に道路が整備されている.TSRの電化と複線化,BAMの支線の整備も進んでいる. ■産 業 モスクワのクレムリンには,武器庫と並ぶ観光スポットである“ダイヤモンド庫”がある.気が遠くなるような多数の大きなダイヤモンド,種々の宝石,金塊な どが展示されている.そこでは,サハ共和国で算出されたダイヤ原石が大きなカップに山と盛られ,コリマ地方(マガダン州)でみつかった30kgにもおよぶ 巨大な金塊などを見ることが出来る.サハ共和国におけるダイヤモンド生産量はロシアの90%以上,世界の約20%を占めているという. また極東ロシアは極東アジアの中で中国と並ぶ石炭の産地であり,また中東地域と並ぶ主要な石油生産地域であることに加え,最大の天然ガス生産地域となっ ている.さらには,鉄鉱石,プラチナ,銀・タングステン・鉛・亜鉛・チタン,そのほかレアメタル,およびニッケルの主要産地でもある.またロシアの金埋蔵 量は南アフリカ・アメリカ合衆国に次いで世界第3位を誇り,その多くが極東ロシア地域にある.加えて極東ロシアは,ウラル山脈から太平洋に渡る広大な森林地帯を擁し,森林面積ではロシア全体の約40%,200億m3以上の森林保有量を有すると言われる. ロシアのシベリア・極東開発の背景には,北極海をはさんで米国と対峙するとともに,埋蔵されている膨大な天然資源があったことが理解できる.現在,極東ロシア北部地域における主要な産業は,これら天然資源の開発関連産業である. サハリン沖石油・天然ガス開発 <執筆中> 東シベリア石油・天然ガス開発 <執筆中> 一方で極東ロシア北部で は,1次産業は厳しい自然条件のもとで,なんとか営まれているのが現状のようである.そんな中,サハ共和国北部などではトナカイの放牧が行われており,貴 重な食肉供給源となっている.北極海沿岸にはわずかの町があるのみで,海が航行可能になる期間も3ヶ月程度のため,漁業は河川および河口部が中心となって いるようである.ただし食卓にはしばしば魚料理が供され,市場では色々な魚が売られている.ただし地元産のほとんどは淡水魚で,海の魚はオホーツク海やカムチャツカ方面で獲ったもの(冷凍)が少しばかり流通する. これとは対照的に,極東ロシアでもカムチャツカやオホーツク海沿岸地域は水産資源に恵まれるとともに,海氷に覆われるのは冬期だけとなるため,水産業が 活発に営まれる.カムチャツカ半島の河川には,太平洋で育つすべてのサケ類が遡上する(シロザケ,キング・サーモン,ピンク・サーモン,レッド・サーモ ン,シルバー・サーモン).沖合のベーリング海は,サケ類,タラ,スケトウダラ,タラバガニなどの好漁場である.オホーツク海は,世界有数の好漁場であ り,サケ類,タラ,スケトウダラ,サンマ,ニシン,タラバガニ,ケガニ,ホタテなど,有用な水産種を含む豊かな資源を擁する.
|